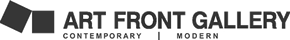プロジェクトProject
Review「水戸部七絵ーその現象性」/ 水戸部七絵個展「Study of Dansaekhwa」「Dansaekhwa」
2025年3月5日からアートフロントギャラリーにて開催された水戸部七絵の個展「Study of Dansaekhwa」(3月5日~16日)および「Dansaekhwa」(3月21日~4月20日)について、水沢勉氏にレビューをご執筆いただきました。
本展では、「Dansaekhwa」というテーマのもと、水戸部による新たな挑戦が発表され、多くの来場者から高い評価をいただきました。
レビューでは、水戸部の作品が持つ深みや進化への探求、制作過程でのエネルギー、そして新作に込められた現象性を鋭く捉えています。
Photo by Hayato Wakabayashi
水沢 勉「水戸部七絵―その現象性」
「水戸部七絵は、昨秋、韓国に滞在し、いつものように驚くべき集中制作をしている。そのときからの新作群は、今回の東京での展示は、発表形式が前後の二つに分かれているように、まさに進行形を感じさせずにおかないものとなった。」
今回の個展での作品発表を作者とともに間近で体験し、わたしはすぐに文章を寄せた。その文章「絵が生まれつつある その現象性」の冒頭である。
絵という、どちらかというとスタティック(静的)で、ホワイトキューブの空間が似合うとされ、固定化されがちな表現ジャンルにおいて(たとえば、ジャクソン・ポロックの代表作であっても)「傑作」とされるものはミュージアム・ピース(美術館所蔵作品)となりがちである。そのような、音楽に喩えるならば、ステージング(舞台化)に類する時空間が絵画にも存在する。
わたしは冒頭につづけて
「いままさに生まれるようとしているものの現状が生の直接性をもって出現するという印象である。「Phenomenon」は「現象」。けして固定されることはない。しかし、それゆえことの大小とは関係なく、世界のあり様そのものをも感じさせるのだ。」
と綴り、さらに
「だから、それを「奇跡」と呼ぶひともいる。」
と書いた。

《Study of Dansaekhwa》展示風景 Photo by Hayato Wakabayashi
今回の連続個展では、去年2024年暮れに韓国広州市に滞在し、制作した一連の人物や家具などをモチーフとする作品が第一期「Study of Dansaekhwa」(2025年3月5日-3月16日)の中心を占めていたのに対して、第二期「Dansaekhwa」(同年3月21日-4月20日)では帰国後の最新作が大作を含め数多くの紹介されている。韓国現代美術の一潮流である「Dansaekhwa(単色画)」に現地で触れたことで、そのモノクロームとマチエールの独自性に関心を持ち、こころ惹かれたことで、それまでの過剰ともいえるほどの奔放な色感に溢れた作品がかなり抑えられ、いままでの自分の制作を「エポケー(括弧入れ)」する態度が前面に現れはじめていた。もちろん、それでも、あのレリーフ状の半立体作品ともいえるほどの大量の絵具の厚みは、基本、変わることはなく、単純に壁に掛けられた絵という風にだけではとらえ切れないものであり、実際、墨色の絵具と石膏を木製の心棒付きの台座に塗って盛った完全に立体の《Kkachi까치》と題された作品もいくつか生まれている。日本語では「かささぎ」。塊としての絵具をひとつの原型として提示する作品であり、動物表現独特の自然な寛ぎを感じさせるけれども、「単色画」に呼応する、必要にして十分な試行を重ねる創作姿勢が、ほのかに、だが確実に、高さ25.5cmという、この作家としてはささやかな規模であっても窺えるのだ。

《Kkachi까치》2025年 / 石膏、アクリル絵具、木 Photo by Hayato Wakabayashi
東京藝術大学の大学院修士課程での卒業制作は、大学の展示空間での発表はままならず、結局、展示中止となってしまった。垂直に5枚のパネルを重ねていくと縦720cmに達するという桁違いの大作であり、厖大な量の絵具が使用されているので総重量もおそらく1tぐらいといってもおかしくないと感じられる作品である。実際、Gallery 21 yo-jでの個展「転ぶ人」(2024年4月25日 - 5月12日)で、メイン・スペースにその1点だけが展示公開されたときも、最下部のパネル1枚は天井高の限界のために足すことはできず、不完全な状態で、まさに「転ぶ人」として展示されたのだ。
具象性は感じられ、長年追求してきた「顔」の巨大化の試みと受け取ることはできるものの、むしろ色彩と物質による抽象性のほうが作品を間近にすると印象に残る作品であった。

《転ぶ人》(部分)2024年 油彩、アクリル、板 Photo by Hayato Wakabayashi
ここまで大胆な表現の高みに不完全なかたちで達した水戸部七絵は、日本を離れ、韓国で、いわゆる現代アートの文脈では、旧知のものとはいえ、現状では主流とはいいがたい「単色画」と対話を静かな孤独な時間を費やして重ねることになる。
そして、絵の発表にまつわる「ステージング」が、まるですぐそばでの囁きのような即興性を湛えはじめたのではなかろうか。
わたしはそれらの作品を今回の個展第二期でまのあたりにしたときこう書いたのだった。
「……韓国の現代絵画の原点というべき「単色画」との現地での対話は、水戸部七絵にいつでも衝動として潜んでいた白黒の対比を描く本人に気づかせるきっかけとなったようだ。奔放ともいえる進行形の弾けるエネルギーは変わらない。しかし、帰国後、最新作は絵を描くという現象をどこかでエポケーさせる静けさを(それさえも絵という現象の一部として)生みだしているように感じられるのだ。」

《Color of Scales : Blue》2025 油彩、顔料、蜜蝋、カンヴァス Photo by Hayato Wakabayashi
画廊の正面の窓から正対することのできる大作《Color of Scales:Blue》は、油彩、顔料でなんとも深い紺色がいつもの分厚い絵具層から滲みでているのだけれど、ぐっと近寄ってみると、画面の上辺あたりに蜜蝋が重ね塗りされていて、そこに白い粉が散らばっているような表情が生まれようとしていたのだった。描いた物質が別のものに繊細に変容していく渦中にある。そのことを感じて、わたしは、最後にこう書いたのだった。
「その往還の現象性。それは、オーストリア、そして、韓国とこの数年、旅して制作する画家そのもののすがたにも重なって「くる/いる」。」
さらにこれからアメリカに向かう予定であるという画家も、作品もまた、さらに繊細で大胆な現象性をいっそう鮮やかに放つ予感がする。
水沢 勉